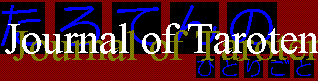
書評 増田直紀 著「海外で研究者になる」2019,中公新書, 880円(C6面:書評, 2019.7.1初稿,2019.7.24訂補)
日本でも大学教育を可視化する統一調査が2020年から実施?(2019.7.24訂補)
以下の「一方,・・」ではじまる段落で書いた「大学への満足度を学生に対して国が調査する統一アンケート」が,わが国でも今年度試行されるという。「大学ごとに学修成果を可視化せよ」などと言ってきた従来の路線に比べると,文部科学省自身が大学の中身を可視化して,大学,学部ごとに結果を整理して公表してあげようというのだから,各大学がやるより公平だろうし効果的だろうが,いきなり現実を突きつけられる大学もありそうだ。高等教育無償化 のときに続いて,大学に共通の物差しをあてはめて,大学の選別をすすめる施策が続いています。
著者は計数工学の研究者で東大からイギリスの大学へ転身
日本の大学は,雑用が増える,予算が減る,大学ランキング で 世界での位置が低下する,など苦境にある。研究者の雇用について,米国,欧州はすでに(人の雇用を「市場」というと,人身売買っぽっくてだめかもしれないが,・・)一体の市場を形成し,中国もそれに参入し,国籍にこだわらず,働き場所を選択するようになってきているにもかかわらず,日本だけが,独自の市場を形成し,研究者の流動の少ない閉鎖的な職域を作っている。海外で働くことがあたりまえになる世の中になってほしいというのが,この本の著者の願いで,実際,著者は,東京大学准教授からイギリスのプリストル大学の上級講師(准教授相当)へ転身した方である。
イギリスの大学には意外に日本的な面もあり・・
「子育ては会議を欠席する正当な理由になる」「トップダウンの意思決定と権限の下部への移譲(たとえば,留学生担当になった人は,留学生に関することは他人に相談することなく決められる)により会議が少ない」「夏休みを教員も事務職員もしっかりとる」「研究費を取ってきたら,授業負担が軽くなる(研究費で代わりの人を雇う)」「定期試験の問題を他の教員がチェックする」などは,日本にはないイギリスの特徴かもしれない。研究室を主催する研究者やそれを目指す人はイギリスでもハードワーカーではあるが,必ずしも,研究室で頑張っているわけではなく,図書館や家庭で頑張っていることが多く,19:00以降に研究室に残っているのはアジア圏からの留学生くらいである,とのこと。
一方で,「クラス担任制度になっていて,学生を子ども扱いする」「授業評価 が重要」「大学への満足度を学生に対して国が調査する統一アンケートがあり,学生に頑張らせすぎるとアンケート結果が悪くなり,学生募集に支障をきたす」など,イギリスの大学教育には,日本の大学の動いている方向 に近いこともある。教育予算は削減方向で,大学が衰退産業であるように見えるのは,成熟国に共通する現象だと著者は言います。
年金などを含めたトータルの損得は
日本人が海外での教員になれない(ならない)理由としては,語学障壁 以外に,年金などを含めたトータルでの社会保障で得失があるとたろてんは考えています。わが国の中で定年前に国立大学から私立大学に異動するのでさえ,退職金制度や年金制度がこのまま維持されるとして,それなりに損だと思うので,海外へ転身すると,さらに将来不安が生じます。それに関する本書の回答はないです。
和文誌はもちろん,英文誌でも日本の学会の論文誌に論文を出してはいけないという
イギリスでは,大学教員の採用において,数10分の面接だけで選考されることはなく,食事会が必ず開催されるらしい。研究業績は履歴書でわかるが,食事会を実施することで,将来同僚としてやっていける人なのかを見極める効果があるという。また,海外の研究者に友人を作っておき,推薦書を頼める人がいることも重要。応募時に記載する研究計画は,いろいろな抱負を挙げるのではなく,ストーリーにしたがって,ひとつのことを明らかにしたいと書くのがよいという。さらに,日本語の論文業績がイギリスで評価されないのはもちろんだが,日本の学会の英文誌 の評価も低いので,海外の論文誌に研究成果を発表するべきだという。論文を出すメディア選び,研究者の友人づくりから海外への転職活動はすでにはじまっていると本書に書かれている。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.