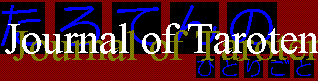
書評:永井孝志ら(2025)「世界は基準値でできている」講談社ブルバックス(C6面:書評, 2025.6.22)
前作の続編です
前作「基準値のからくり(2014)」の続編です。10年ぶりに改定したというか,新しい基準について論じたという感じです。著者順は変わりました。
第1章はスポーツ競技で女子として出場するための基準
「1964年の東京オリンピックの女子のメダリストの1/4以上が本当は女子ではなかったのでは」という話が本書で紹介され,ちょっとショッキングです。女子の集団のなかでもたぐい稀な身体的能力の持ち主だけを集めれば,確かに,本当は女子でない人が多いことはありそう。共産圏で女子だけ記録が伸びる疑惑もあり,国威発揚のためのドーピングもありました。歴史的には,「医師による目視 → 染色体検査 → テストステロン濃度基準 → 迷走」となっていることが本書で紹介されており,染色体構成が「XX」か「XY」かというような単純な話でないそうです。
PFASの水道水質準値
PFASは相当古い問題で本ウェブサイトでも 2006年の記事 にすでに紹介しているものだが,近年,再注目されている。本書によれば,製造販売が中止され,曝露量が低減している今になって,厳しい規制値が水道水に設定されることが紹介され,最大の曝露源である食品が見過ごされているとされている。本書によれば,「問題が小さくなってから,問題の小さい方をたたいてしまう」という ダイオキシンのときと同じ構図 が繰り返されているということのようです。
新型コロナ対策
10年前の前作 から今回の著作に至る間にあった大きな話題として,新型コロナウイルスの問題 があります。本書では,「15分間マスクを外して一緒にいると濃厚接触者になる」という基準が導入されたことで,「給食の時間に教員がストップウォッチを持って,14分を測り,食べ終わっていない学生にいったんマスクを着用させ(そこでリセット),そして,再度,マスクを外して食べさせる」という誰にとっても得でない対策が実施されたことを紹介し,基準の使い方の問題点としている。
「どのような社会を生きたいか」という問題
基準値は,科学をベースとしながらも,「どのような社会を生きたいか」という意思が大きく影響するという指摘はその通り。基準が「甘すぎる」とか「厳しすぎる」とかいった不平を低減させるには,立場の違う人が妥協点を探るべきだろうが,前作と今回の著書の10年の間で,トランプ(米国大統領)や斎藤元彦(兵庫県知事)を持ち出すまでもなく,社会の分断化が進み,立場の違う人が妥協点を探ることは一層難しくなっています。みんなが合理的にリスクを定量化し,自分事として考えることはもはや不可能ではないかと,改めて本書を読んで感じた。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.