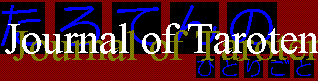
環境工学フォーラム函館行って来ました (C2面:環境衛生工学,2006.11.19)
北斗星で行って来ました
今回,出張扱いでなく休暇で言ってきたので,行きはのんびり北斗星,帰りも,昼間の特急+新幹線で行って来ました。北斗星も結構乗ってたし,帰りの特急も2両増結してほぼ空席なしだから,まあまあ青函トンネルも使われていると言うことか。北斗星も,まだまだ廃止される心配はなさそうに感じたが,仮に,空寝台なしでもJRにとって儲かる列車でないのも確かである。
フォーラム開会式で,たろてん,最初に昨年の奨励賞の賞状をもらった。自分で投票して自分で賞をもらっているのだから,しょうがないが,まあ,もらえたということは他の人も投票してくれたと言うことでしょう。今年のフォーラムでも,この当該論文は,かなり引用されていたので,ちょっと,うれしかったです。
医薬品関連は京大の独演場
今回,我々は,医薬品関連は出さなかったが,医薬品 関連はまさに京大の田中宏明先生たちの発表の独演場だった。紫外線処理では,処理水量あたりの照射量の評価手法が質疑されていた。紫外線で消毒はできても物質の分解に用いるには相当に照射量が多く不経済になりやすい。また,微量物質の添加方法として,溶媒を乾固し水に再溶解したそうだがこれも心配な方法である。藻類成長阻害試験による毒性評価,下水処理場実態調査,分析法の検討と4件続けて京大の発表だった。
微量物質関連では,他に,活性炭吸着を扱った岐阜大の研究では,生物活性炭の効果が限定的で,単なる粒状活性炭の方が良いとの報告があり,我々の研究とも類似であった。このグループは底泥中での分解についても発表したが,易分解物質の共存は当該物質の分解に競合的に働くわけではない,とのことであった。八十島さんたちの活性汚泥での吸着挙動では,汚泥の不活性化の手法に問題がありそうに感じた。また,京大の PFOS, PFOA の挙動に対して,たろてんが化合物の親水/疎水との関連を質問したら,松井三郎先生よりlog Kowでは界面活性剤の挙動を理解することができないとの説明があった。さらに同じ京大のグループが水道水中のこの物質に対する発表を「世界ではじめて」おこなったとのことだった。北大のコンポストトイレでの医薬品挙動の発表では,コンポストトイレ中での医薬品の分解は生物反応ではない,という驚きの結果が報告されていた。
谷川岳周辺の窒素の流出,意外に面白かった
青井先生たちがやっている 谷川岳近辺 での窒素の流出の話題だが,たろてんは,これまで,「そんなことどうでもええやん」と思っていた。確かに,大局的に見て,どうでもいいことなのだとは思うが,首都圏の一大汚染源を抱えて,世界的も最大規模の窒素飽和現象がこの付近の土壌で起きている,と言われると,ちょっと,科学的好奇心を刺激された。ようするに,岩盤からの流出と森林からの流出を比較して,森林からの流出水のほうが窒素濃度が高い状態を窒素飽和と言うのだそうです。谷川岳,湯檜曽川付近と言うのは,たろてんは土地勘がある。
さらに,降下してくる窒素は,硝酸態(大気中のNOxに起因)と普通思ってしまうが,かなりアンモニアの寄与が大きく,しかも,アンモニアの排出源のかなりの部分を自動車が占めると言う。大気汚染というと今までNOxばかり気にしてきたが,窒素分という意味では,アンモニアも重要なのかもしれない。この付近にある関越自動車道のトンネルの排気塔を調べさせてほしいと言う願いを道路公団(東日本道路??)に青井さんたちがしているのだそうですが,あまり公団(会社?)は良い顔をしてくれないようです。たろてんも,廃棄物処分場を管理している人たちとの間の折衝ではあまり良い思いをしたことがないが,道路公団(が分社化された会社)の人はぜひ,余裕のある態度で,こうした調査を受け入れてほしい。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.