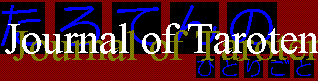
書評:吉見俊哉 著(2021)「大学は何処へ」岩波新書,900円 (C6面:書評,2021.5.08)
世界の中で存在感を失いつつある日本の大学
本書は,日本の大学が量的に膨張する中で,世界でのランキングを大きく落としている ことを考察対象としている点では,以前紹介した 豊田長康著 (2019)「科学立国の危機〜失速する日本の研究力」と同じであり,目線が,地方国立大学学長の視点から旧帝大系国立大学文科系教授の視点へと変化したものである。第二次世界大戦に端を発する理科系の膨張を快く思っていない記述がみられるが,著者はもともと東京大学理科I類入学の方なので,生粋の文科系という方ではない。
学年暦がグローバル化できない理由
教育・研究のグローバル化 が重要だと言われ続けているのに反して,わが国の大学生の内向き志向は年々強まり,2000年時点に比べて日本から米国への留学生は半減,中国や韓国に遠く及ばない状況である。新型コロナウイルス感染症によって,さらなる若者の内向き化が懸念される中,高等学校休校措置によって,再度,大学の秋入学が急浮上し,泡のように消えた。学年暦を国際化する提言の歴史は古く,1980年ごろから何度も検討され,そのたびに,できない理由があれこれ並べられて頓挫してきたことが本書で述べられている。2学期制をクオーター制へ移行し,4月〜5月を第一クオーター,6月〜8月を長い夏休み,9月〜2月に第二〜第四クォーターとすれば,入学時期を4月にしたままでも,大学生が留学しやすい(海外経験を積みやすい)学年暦になると本書では提案されています。
大学教育の中身への社会の関心は低く,リカレント教育は必要とされない
人生100年時代においては,学びなおしの機会が必須であり,リカレント教育の役割が大学にある,とよく言われる。ところが,わが国大学入学者に占める25歳以上比率は2.5%であり,この値は,OECD諸国の平均16.6%に比較して桁違いに小さい。しかも,この2.5%は通信制を含めた値であり,通学生だけに限定すれば1%である。解雇が極端に制限され,同じ職場に長くいればいるほど得をする 我が国の雇用,給与・年金体系も崩れそうで崩れておらず,リカレント教育は,我が国では,個人にとって不要であり,企業も企業外で異なる経験をした人を厚遇することはない。日本社会は大学入試には関心があり,学歴ラベルを個人に貼る機能を大学へ期待しているが,大学教育の中身には期待していないので,誰も学びなおしのために大学に行こうとは思わない,と本書では分析されている。
自らの首を絞め続ける大学
大学における若手研究者の苦難(助教を削減し教授を増員)も,大学院重点化に伴う大学院レベルの低下も,すべては大学自身が望んだことで,誰かが大学へ押し付けたことではない。一方,経済界や行政から大学に対して,学長のリーダーシップで資源を集中することが求められるが,一般の会社の経営と違って,「予算」や「ポスト」を資源と考えて集中投入しても,大学では効果が極めて乏しい,と本書では分析されています。大学におけるもっとも大切な資源は「思索する時間」であると主張されています。最重要資源が「時間」であるとの主張に対しては,「予算」や「ポスト」の獲得を進めてきた理科系の教員に同意しにくい内容が含まれているが,確かに,「時間」は,様々な改革で容易に失われてしまう資源で,その確保は重要課題です。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.