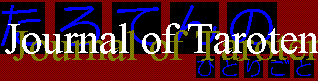
書評 豊田長康著 (2019)「科学立国の危機〜失速する日本の研究力」東洋経済新報社,2600円 (C6面:書評,2020.10.24)
学術論文の量と質をデータをもとに解析
本書は,日本の研究力の低下 に関する書籍である。主な論点は,わが国の学術論文数やその質が何によって決まってきたかである。論文数や被引用回数などを従属変数,GDPや常勤研究者数や研究費を説明変数として,豊富なデータで仮説が検証されます。ただ,536ページの分厚い本のほとんどが生データの感があり,少し読みにくいかな,と思います。逆に生データで検証しないと気が済まない疑り深い人にはいい本だといえるでしょう。
地方国立大学の立場から「選択と集中」を批判
本書の著者は元三重大学学長ということで,本書の結論には,彼が地方国立大学の学長であったということが大きく影響していると考えられます。つまり,2004年の法人化以降毎年1%ずつ削減された運営費交付金が地方国立大学の困窮化を生じ,研究者数が減少した一方で,「選択と集中」の恩恵を受けたはずの 旧帝大系の有力大学でも論文数が増えなかったこと が解析されています。本書は地方国立大学の立場から書かれているので,私立大学の立場 からの読者であれば,最後は国に助けてもらおうという甘えを本書に感じるかもしれません。
論文の数を決めるものは
「選択と集中」は,赤字事業をだらだら続けることを避ける経営観点として重要であるが,そもそも,「選択と集中」で切られた学術分野や地方国立大学は本当に赤字事業だったのかということが本書で問われます。投下した金額あたりの論文数で評価すると,選択と集中の恩恵を受けた部門のほうが生産性が悪いことがデータで語られます。よく言われることですが,基盤(C)で500万円投下するより基盤(A)で5000万円投下したほうが,科研費の採択課題数 あたりの成果論文数はやや多いが,研究者数(分担者含む)あたりに換算すると成果件数は同じで,研究費あたりでみると,はるかに基盤(C)の方が優れたお金の使い方になっている,ということのようです。
論文の質で見ても少額研究費の効率の良さが示される
高額の研究費を得ている研究課題が,困難な問題に先端的方法で挑んでいると考えれば,高額研究課題の研究で,研究費あたりの論文数が少なくなるのはあたり前に思える。ただ,本書では,論文の「数」ではなく,「質」で評価しても,少額研究費の良質論文生産性の高さ(言い換えれば,大型研究の効率の悪さ)が示されるとしている。結局,研究者数で論文数が大方決まり,総論文数で良質論文数が決まっているので,選択と集中を進めて,研究者数を減らしたことが,日本の研究力の失速の原因になったというのが,本書の結論です。研究を実質的にやめた教員についての記述は本書には明示がないが,本書の記述からは,研究をやめる原因は,直接の研究費が削減された,という効果より,運営費交付金の減額で退職教員の後任人員を凍結したことが教育負担と雑用負担の増加につながり,研究する気が萎えた,ということのように読めます。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.