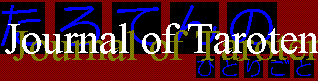
大きく変動しやすい大腸菌数の測定値(C2面:環境衛生工学, 2025.3.31)
大きく印象の異なる我々の測定と国土交通省測定
同じ場所で測定しても,水質は変動するが,生物化学的酸素要求量(BOD)とか全窒素(TN)とかいったmg/Lで測定する項目では,普段,2 mg/Lの場所で20 mg/Lになるとか,そんな変動幅です。しかし,大腸菌数は,変動幅が非常に大きい。図は,合流式下水道の影響を受ける鶴見川新横浜付近での2024年の水質の測定値である。さらに,茶色が我々の測定,青色が国土交通省の測定である。この2つのプロット,ずいぶん,印象が異なって見えないだろうか。
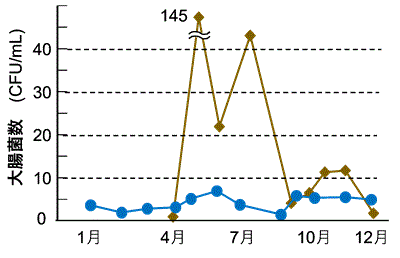
2024年の鶴見川新横浜付近の水質測定値
おそらくは雨の影響を排除するかどうかでここまで印象が異なる
我々の測定は,国土交通省の測定より高めの印象を与えるが,これは,我々の測定では,事前に決めたスケジュール重視で,ランダムに採水がされているためである。とくに,図の異常値(145 CFU/mL)は,雨の中採水した日であって,我々の測定のうち雨の影響のない日に測定したデータでは,国土交通省の測定とで,それほど変わらない。一方,国土交通省測定では,昭和46年の環境庁通達「採水日は、採水日前において比較的晴天が続き水質が安定している日を選ぶこととする」が守られているため,低目になるのだろう。この通達がなければ,合流式下水道 は違法になってしまいます。
本研究は,T. Urase and S. Goto (2025): A case study on factors influencing Escherichia coli concentrations in an urban river draining a fully sewered area, Water 17(20), 3026 (DOI).として発表しました。
国土交通省の測定はどのような日に行われているのか
河川のいわゆる生活環境項目の測定では,「公共用水域が通常の状態(河川にあつては低水量以上の流量がある場合・・(中略)・・)の下にある場合に、それぞれ適宜行なうこととする。」と定められているのだが,これは,「流量が小さいと排水が希釈されないから,流量が異常に少ないときは基準を守れなくても仕方がないですね」という意味で,雨の日に測定値が異常に高くなる大腸菌を想定した注ではない。さらに大腸菌の結果の解釈として「大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(中略))とする」と定められているのだが,月1回測定するとして,「12回のうち,1回は基準超過してもいいよ」という意味になる。先日の水環境学会年会で pseudo水の天使さんが「年4回測定に合理化する動きが 大腸菌の基準達成 に与える影響が心配」というようなことを言ってました(4回の90%だと,4回中4回になるという懸念)。
「水質が安定している日」をどう判定しているのか
国土交通省測定で,「水質が安定している日」をどのように定めているのだろう。鶴見川の国土交通省採水日,その前日,前々日の降雨状況を気象庁のウェブサイトで確認したが,採水72時間以内の総降雨量が10 mm以下というわけではなく,それなりに雨があったときにも測定されているようでした。でも大腸菌数が異常に大きくならない日が選ばれているようにも見えます。「水質が安定している日」は案外,事前にはわからないにもかかわらずです。そういうことで,水環境学会年会での発表「公共用水域の水質測定が水曜の午前採水に偏っている(東洋大, P-A-49)」に興味を持ちました。
まさか,測定してから「水質が安定している日」を決めていないか
以前,企業から排水管理の受託分析を請け負う分析コンサルにアルバイトに入っていた際に,予備の採水を必ずしていたことを思い出しました。n-Hexなど変動の大きいものについて,「基準値を超えたら,もう一本の予備のサンプルを再分析」していました。これが,適法なのか,違法なのか,今となってはわからないが,「日間平均値を測定した」と言えなくもないので,まあ適法なのでしょう。ただ,公共用水域の水質測定が「大腸菌を測ってみて,値が高い場合は,予備の試料からもう一度測定する」というような実践になっているとしたら,この値をどのように解釈すればよいのか,かなり「?」な印象です。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.