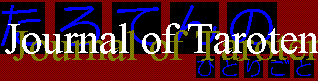
下水道協会誌の興味深い記事(C2面:環境衛生工学, 2025.3.25)
スマホの上において生物顕微鏡になる器具
本サイトでは,これまでの2回,下水道協会誌の面白い記事「スイスの下水処理水中の医薬品対策」,「1,4-ジオキサンの共代謝」を紹介しました。で,今回は,3回目(Vol. 62, No. 749, 2025年3月号)で,第61回下水道研究発表会の各賞受賞の記事から。まずは,日本語ポスター部門再優秀賞の「スマホの上において生物顕微鏡になる器具(水ing)」から。現場でスマホとこの器具があれば,活性汚泥を撮影し,スマホでどこかへ送って,生物群集を診断してもらうことができます。学生の野外実習などにもいいかなと思いました。
パレスチナでの下水処理水・汚泥の有効利用
水環境分野で海外プロジェクトの研究発表を見ることは珍しくないが,英語ポスター部門最優秀賞「Palestine, Jerichoでの下水処理水,下水汚泥の有効利用(NJS)」では,内容は平凡だと思うが,対象国がホットです(Jerichoはいわゆるヨルダン川西岸地区のようで,ガザではないです)。これまで数回,本サイトでも イスラエル/パレスチナの話題 を扱ってきています。こうした発表に賞を出すのって,政治的な勇気が必要なのか,そうでもなくすんなり決まるのか,気になりました。
透析排水が下水管を痛める問題
日本語部門の優秀賞は「透析排水が下水管を痛める問題(東京都下水道局)」で,八潮の道路陥没の事件の際に,「透析排水が原因なんじゃあ」と一部で疑われていたため,昨夏の発表時点ではそれほど注目されたのかはわからないけど,いまとなっては,ちょっと,ホットスポットです。関係ないけど2025年1月〜3月期のテレビドラマのうちで,日テレ系の「ホットスポット」が最優秀でした。
次世代型メタン発酵
受賞記事以外にも,静岡県湖西市での次世代型メタン発酵の記事が興味深かったです。消化槽に設けた疎水性中空糸膜の内側に60℃の温水を流し,膜を介して気体として消化液からアンモニアと炭酸を引き抜き,メタン生成菌の活性を保つもので,気体透過膜の新たな使い方として面白いと思いました。豊橋技科大が絡んでいます。ここまでふれていませんが,今号の特集は能登半島地震で,それはそれで,昨今の設計の考え方を知るのによいと思います。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.