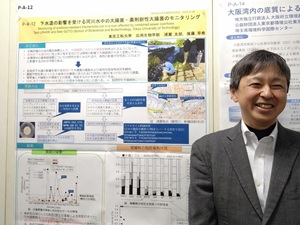
たろてんのポスター
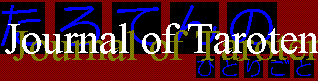
この時期は卒業式とかぶります。ということで,口頭発表に申し込んで3日目になってしまうと困るので,おそらく1日目か2日目になり,仮に(ありそうもないが)3日目と言われたとしても,ポスター貼り逃げでも大丈夫なポスター発表にたろてん自身のものは申し込むことにして,学生の口頭発表2件と助教の先生の同様の理由によるポスター発表1件を合わせて,今回,合計4件の発表をしました。
1) 臭気物質ハロゲン化アニソールの生成細菌の特性評価,水環境学会年会, 59, pp68, 1-F-10-4 (札幌,2025年3月17日発表)
2) Bacterial community in the permeate of microfiltration membranes with different pore sizes,水環境学会年会, 59, pp84, 1-G-11-4 (札幌,2025年3月17日発表)
3) 生分解性プラスチック分解による土壌微生物群集構造への影響,水環境学会年会, 59, pp661, P-J-03 (札幌,2025年3月17日発表)
4) 下水道の影響を受ける河川水中の大腸菌・薬剤耐性大腸菌のモニタリング,水環境学会年会, 59, pp496, P-A-12 (札幌,2025年3月18日発表)
気になった発表をいくつか。北大のグループは,1-G-09-1でアーキアに寄生するPatescibacteriaグループの微小細菌の新種の発見を報告した。1-G-9-2で金沢大のグループは,Comammox(「アンモニアから亜硝酸」とか「亜硝酸から硝酸」ではなく,アンモニアから硝酸への反応をひとつの細菌のなかで完結するものをこう呼ぶ)を行うNitrospiraの検出法を紹介した。1-G-09-3では京都大のグループが活性汚泥から84個のMAG(Metagenome Assembled Genome)を得て,どのような脱窒酵素配列を持つのかを検討した。1-G-10-1では広島大のグループがPatescibacteriaのMAGを112個取得し,それらを アンプリコンシーケンス の結果と比較していた。彼らの主目的ではないが,よく使うV3-V4領域のプライマーより,V4-Modifiedのプライマーがこのグループの細菌の解析に適しているらしい。1-G-10-2で産総研のグループは,低密度培養条件下でMycobacteriaceaeが優占することを報告していた。1-G-11-1で横国大のグループが排水処理16S rRNAデータベースとしてMiDAS(Dueholm et al, Nature Communications, 13, 1908(2022))というものを使用するということを述べていた。また,アナモックス関係の研究が多くみられました。
Mycobacterium属は,結核菌 M. tuberculosis,らい菌 M. leprae,肺MAC M. avium complex,肺アブセッサス症 M. abscessus complex,などを含むちょっと怖い属で,とくに後2者は最近,罹患者が激増中のようです。分子生物学的知見に基づき,2018年にいくつかの分家(分属?)が生じ,たろてんたちが,トリトリクロロアニソール生成細菌だとしている(サウナなんかの隣にある)冷水浴槽から単離したMycolicibacterium(1-F-10-4)もその分属のひとつです(現在,全ゲノム解読中で,その結果によって多分BSL2)。今回の学会では,このMycobacterium属についての発表を多く見ました。活性汚泥の微生物密度が低いと同 科が群集中で増える(産総研,1-G-10-2)とか,環境中で大腸菌のような減少を示さないグループであるとか(国環研, P-J-07; 宮崎大,3-C-14-3),水道水栓でのアメーバを宿主とする細菌として,Legionella属と同様に大切であるとか(東大, 2-E-9-3),多くのMycobacterium属についての研究が見られました。
カルバペネマーゼ遺伝子を調べたら,GESが多かった(東京科学大, 3-I-9-1; 東大, 3-I-9-2)というのは,たろてんたちの知見(DOI:10.3390/antibiotics11070917)とも一致します。ほかに,インテグロンを指標とした研究(北里大, 3-I-10-4; 東大, 1-I-16-3),アジアの途上国での状況(金沢大, 3-I-11-3)など多くの耐性関連の発表がされた。たろてんは,基本的には,下水道(たとえば,活性汚泥中)において,菌種の壁を変えて耐性遺伝子が伝達していることの重要性は低そうに思っていたのですが,伝達についての発表も数件ありました(北里大, 1-I-16-1; 立命館・京都大, 3-I-9-4)。プラスチックごみ表面からの薬剤耐性菌について発表もあった(中央大, 3-I-10-1)。
1-C-15-3で京都大のグループは熱分解GC/MSによるマイクロプラスチックの定量に際して,300℃の加熱で揮発性成分を除去したうえで,600℃でポリマーを熱分解する方法を報告した。気体透過膜による酸素供給に関する発表で,曝気をしないことでN2O発生抑制になるそうです。タイヤ摩耗粒子は最大のマイクロプラスチック源 のようなのですが,そのサケ科魚類への毒性がタイヤゴム酸化防止剤の6PPDに由来する6PPDキノンという物質によることに関する発表が数件ありました(京都大, 2-D-13-3; いであ, P-J-16; 名古屋市環科セ, P-A-67; 産総研, P-B-6など)。2-B-14-3では,東大のグループが下水処理水の臭気について発表し,TCAについて我々の研究 を引用してくれていました。ありがとうございます。公共用水域の水質測定が水曜の午前採水に偏っている(東洋大, P-A-49),大腸菌が環境中のバイオフィルム内で増殖する(北大,L-48),家庭の流しなどに発生するピンクのバイオフィルムでMethylobacteriumが優占している(兵庫県大,L-92),なども興味深いです。膜関連の発表では,開発企業との間の秘密が多そうでした(信州大,P-D-17)。
今回の札幌開催の水環境学会の年会は,口頭発表では立ち見,ポスター発表では大混雑,セッションの変わり目ではトイレが大行列という感じで,盛況と言えば盛況なのだが,やや狭苦しい印象であった。こうした混雑もあってか,休憩から会場にもどってきた喫煙者による「たばこの臭い」が気になると言っていた参加者もいました。学生と懇親のために行った札幌駅近くの飲み屋さんも喫煙OKで,北海道はやや煙たい土地柄かも知れません。
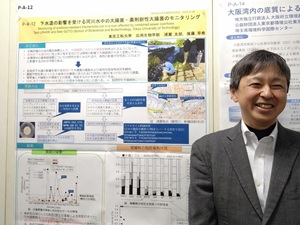

Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.