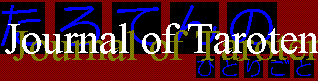
大学進学率の上限に関する一考察(C4面:大学教育, 2025.11.06)
大学進学率はどこまで上がる
少子化による18歳人口の減少により,多くの大学が入学者の確保に苦労 しはじめている。2024学校基本調査(文科省)によれば,大学(学部)進学率は59%,短大進学率3%(最盛期の13%(1994)から激減),専門学校進学率24%となっている。東京都の大学進学率が73%くらいだというので,地方の大学進学率が東京並みに上昇すれば,あるいは,経済的支援(高等教育無償化制度など)が充実すれば,国全体の進学率が上がるとの楽観論もあるが,すでに高等学校卒業者の87%が何らかの高等教育機関に進学している勘定なので,マーケット拡大の余地は小さい。
女子の大学進学率は上昇したが,そろそろ頭打ち。大学院はまだ伸びしろあり?
たろてんが大学に入学した1986年の女性の大学進学率は13%なので,ほとんどの女性は高卒もしくは短大卒だったことになります(貴重な女性大卒,しかも,理学博士を1名いただきました)。いまでは,大学進学率に男女の差はほとんどありません(男性62%、女性56%,2024)。一方,我が国の大学卒業者を分母とした大学院進学率は,2019年のデータしか容易には見つけられなかったですが,男性15%,女性6%で,こちらは,依然として,男優勢です。博士課程ではどうかということで,農学・環境分野の特別研究員DC1(2026年度)の申請件数を調べると,男性355名,女性177名でした(女性が多そうな生命系でもほぼ同じ比率)。DC1の最近の申請書式にフィットしやすい「TOEIC 900点で,海外との共同研究を主体的に進めました」とか申請書に書きそうなバイリンギャル(ほとんど死語)がDC1申請者に多い感覚だったが,データとしては依然として,男性が多いです。工学系でのDC1申請では86%が男性。
通信制高校の在籍者の大幅増加
不登校の人の割合は,その学年の全人口に対して,小学生で2%,中学生で6% (2025)という。そして,この不登校の一部が引きこもりに移行し,内閣府による2023年発表の調査結果によれば,15歳~39歳人口の2%が引きこもりと推計されている。ただ,不登校の6% → 引きこもりの2%と減っており,引きこもりの2%には,就職してみて引きこもりになる人も相当含まれるから,中学不登校者の卒業後の一般的な進路は「引きこもり」ではなく「進学(とくに通信制高校への進学)」であると考えられる。
実際,通信制高校の在籍者数はこの5年で1.5倍に増え,全国の高校生に占める割合は9.6% (2025)だった。何らかの学力面や履修科目面で不安のある高校生が通信制高校に多く,年明けの一般選抜入試を敬遠し,年内の総合型選抜試験で大学受験する場合 が多くみられるが,通信制高校から送られてくる評定平均が5.0(満点)のケースも多く,それを総合型選抜でどう評価してよいのか,大学にも悩みが生じてしまう。
特別支援教育の対象者への進学支援
視覚障害,聴覚障害の人が大学に入学し,大学で学んだあと,優良企業に就職するのをときどき観察します。「聴覚障害だと化学実験で注意が届かなくて,事故があったらどうする」という議論もあるし,受け入れ態勢を整備しないで,受け入れることが最も無責任だとは思うが,こうした方のそれぞれの未来へ向けての大学進学,大学生活,進路希望をたろてんは支援します。
2022年の特別支援学校あるいは特別支援学級に在籍する学生数は4.6%で,通常の学級で指導を受けているもの1.7%も加えると特別支援教育の対象者は6.3%であり,さらに,2022年の文部科学省調査では,普通学級のなかにも注意欠陥多動性障害(ADHD)や学習障害(LD),高機能自閉症等が合計9%在籍すると報告されている。これらの方々のなかにも,潜在的には大学進学の意思や能力を持った方も含まれていると考えられます。ただし,個々の事情に配慮した受け入れ態勢(たとえば,聴覚障害者向け文字起こしに対応した講義室の音響システム)が大学側に必要であり,私立大学にその労をとらせるのであれば,税金による支援をお願いしたいところです。
もはや例外的ではない
ということで,不登校,引きこもり,通信制高校,特別支援教育対象者,ADHDやLDなどの人数は,社会の例外というには,かなり多く,合計すれば2割~3割になりそうです。しかも,近年,大きく増加しています。「これまで見過ごされていた障害が医療技術の発達で発見され,早期支援につながっている」のなら,こうした人の数が増加するのは社会がよい方向へ向かっていることになりますが,「スマホ利用の副作用で社会性がなくなっている」とか,「保護者の生活環境が崩壊しており,学校へ行くことの優先順位が下がっている」ということであるのなら,個人の問題ではなく社会の問題です。このように,18歳人口には,いろいろ困難を抱えた人が多く含まれており,大学進学率の上限を形成していると本稿では考察します。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.