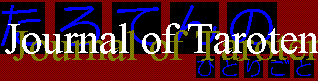
生態学の講義 (C4面:大学教育,初稿2008.9.30,学生の評価を追加2017.10.20)
(2017.10.20 学生の評価を追加)
本講義もすでに8年担当して,内容も洗練されてきました。洗練された内容が理解されやすいかはまた別問題ですが,この分野を体系的に教えることができているとは感じます。以下は外部サイトに書き込まれた授業の評価。内容充実度は満点で,「きいていて飽きない」とのコメントで,うれしいです。「単位が取りにくい講義」との評価になっていますが,85%以上の単位取得率になっていると思うので,選択科目としては標準的だろう。(試験問題の 出題例1, 出題例2, 出題例3, 関連した演習)
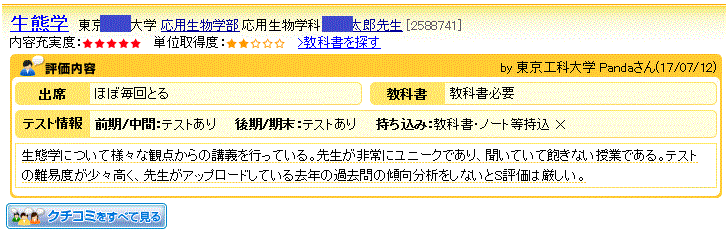
生態学は衛生工学とはかなり遠いです
水質・水処理関係以外に「生態学」の講義を担当することになりました。水質や水処理の分野は,純粋に人工の施設なので,衛生工学における環境の捉え方も,やはり人間中心で,それはそれでよいことです。ただ,自然の場を研究する生態学とは,少し学問の視点が異なるようです。
科学として教えるためには教科書を指定
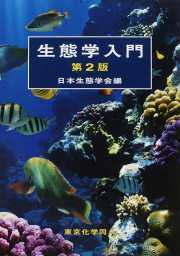 生態学のような講義を「お話学問」だとして,厳密な学問体系から切り離し,特定の思想を教えようとする人が東工大時代にいました。これは,水工学など物理を基盤として環境に乗り込んできた人が,厳密な体系から一気に環境のあいまい領域に迷い込んで陥るミスです。「正しい環境の捉え方を教育したい」などといっていましたが,「正しい」環境の捉え方を教育する前に,環境の捉え方を教育する必要があります。右の本を教科書として指定しました。
生態学のような講義を「お話学問」だとして,厳密な学問体系から切り離し,特定の思想を教えようとする人が東工大時代にいました。これは,水工学など物理を基盤として環境に乗り込んできた人が,厳密な体系から一気に環境のあいまい領域に迷い込んで陥るミスです。「正しい環境の捉え方を教育したい」などといっていましたが,「正しい」環境の捉え方を教育する前に,環境の捉え方を教育する必要があります。右の本を教科書として指定しました。
生態学の対象は・・
生物の分野では,分子生物学などの細かい分野が流行中。一方,生態学は生物と環境の相互作用の学問であって,その興味の範囲は,やや大きい対象となります。生態学は,関連する進化や分類も含めて,なかなか面白い分野だと勉強してみて改めて感じました。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.