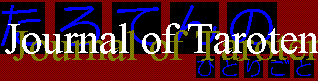
割引率と組織運営(C5面:近況, 2025.4.28)
論文の「△△△に役立つ」「はじめての△△△」
科学技術論文を読んだときに,「この研究は,△△△に役立つ」と書いてあったときに,「すごいなあ,これで△△△も解決するんだ」と思う研究者はまずいない。科学技術論文に慣れ親しんだ人ほど,「どう役に立つのかあいまい。たぶん,たいして役に立たない研究なんだろうな」と思うでしょう。「我々の知る限り,本研究は,△△△についてのはじめての報告です」と論文に書かれているとすれば,これも「はじめてなんてすごい」と思うことはなく,「もしかしたら,△△△に限れば,狭い意味では,はじめてかも知れないけど,似たような研究はたくさんある」と思うでしょう。研究者も厚かましくなっている面もあるし,しっかり自分を主張しないと研究者として生き延びることができない世界になっているようです。だから論文を読む立場でも,割引率をかけて 論文を読むことになります。
論文はプロ相手,でも,組織運営でも同様の・・
論文は,プロ相手の出版物なので,「役立つ」「世界ではじめて」と大げさに書いても,プロは割引率をかけて読むので,それなりの正しい実相が伝わります。一方,総理大臣だったり,大学の学長/学部長/研究科長 だったり,独立行政法人の理事長だったり,学術会議の会長 だったり,そういう立場の人も,実態が大したことがないものを大げさに言い,成果を強調する場面が増えているように思います。これも,きく側が割引率をかけてきいていれば,そう大きな問題ではないのでしょうが,大したことがないものの成果を強調するのもストレスのかかる仕事だなと感心します。これは大げさに言うことを批判しているわけではなく,純粋に「大変な仕事だな」「たくさん給料もらって当然だな」という評価で述べています。
組織人として最低限の成果主張は礼儀
組織で働いている以上,成果は強調した方がいいし,論文を書くにしても,「何の役に立つのかわからない論文」や「はじめての発見でもない論文」は,よい雑誌に掲載されません。だから,多少大げさに言うことは,世の中で生きていくための礼儀みたいなもので,たろてんもその礼儀にのっとった行動を取るときもあります。「黙っていても伝わる」「内々で,根拠なしで,意思決定する」というような文化が失われたために,大げさ社会が到来したとも言えそうで,透明な社会になった良い面が大げさ社会にありそうです。一方で,大げさ社会にまったく疑問を持たないとすれば,これまた,おかしなことだとも思っています。大げさは,必要最低限にしたいものです。
Copyright © 2000-2026, Taroten. All rights reserved. J. of Taroten.